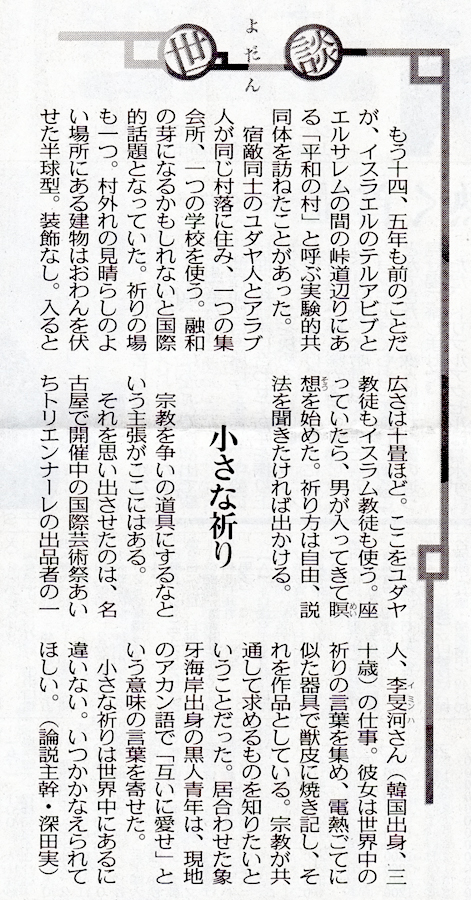李 旻河(イ・ミンハ):渇望、刻み込まれた「人間たる所以」の跡
朴 世姸(パク・セヨン、美術理論)
イ・ミンハは、紙と革に祈りを書く作業をして来た。そのために作家は多国語の祈りを収集し、それらを一文字ずつ筆写する。そしてその過程を経た画面には国家と宗派、人種を超えて集まった多様な言語の祈りが交差、重畳し創り上げられた多彩な形跡が残る。
このように祈りというテキストを用いて作業をしているため、一見既成宗教に対して表現しようとしたものように考えられるが、実際に作家が注目しているのは、「繰り返してある行為を行う人々の態度や心得」である。作家ノートによると「祈る」行為は、「聖」と「俗」という人間性のジレンマが表出される接点に見られ、人間なら誰でも自分の安慰を最優先にする本能を持っているが、それと共に利他的であり、より高い次元を志向する心も持っているのではないかという話だ。すなわち、作家は祈りの目的が世俗的なものであろうが、崇高なものを志向することであろうが、何かを切に求めて望む祈りという行為自体が持つ真実性に注目し、「祈り」を人間の本質、人間たる所為を最もよく表せるテーマであると想定したのである。
祈りを筆写するに至った過去の作品では、韓紙に筆と墨で繰り返し線を描いた作品がある。薄墨を重ね、反復する「線描」行為を通じて、作家は無我の境地に近い没入を経験し、反復行為の修行的な側面を自覚できたのであろう。筆写というものは、やはり昔から現在まで行われてきた宗教的な修練の一つの方法であるということを思うと、線描行為と経典や祈りを筆写する行為の類似性に着目し、現在の制作へ続いていることが分かる。
最初、紙に鉛筆で筆写することで始まった作業は、その材料が革と焼きごてへと変わり、続けられてきた。興味深いところは、材料を紙から革に変えたきっかけが、狂牛病に関するニュースだったということだ。人間のために大量殺肉される動物を見て、人間性を失っていく過程を見たのである。また作家は昔から疎かにあしらわれ賎民の業であった革産業に内包された差別と抑圧の歴史まで思い浮かべる。このような連想作用は、作家がこれらの問題を始め、戦争や宗教紛争など、人間たる所以とその喪失について感心も持ち、悩んで来たことが素地になっている。
鞣した牛や豚、羊革の上に焼きごてで祈りを焼き刻む作業。革の上に熱くなった焼きごてで焼き刻むと、革が焼ける臭いと煙が生じるが、作家はその臭いと煙から戦争や飢餓、虐殺などの問題を思い出す。聖なる祈りを筆写すると同時に肉が焼かれる臭いが生じる。そさらに革を焼き刻み、文字を刻印して行く過程は破壊的な性格を帯びている。このように矛盾した属性が生じる点が、作家が感心を持っていた複数の問題を喚起させ、祈りの筆写作業は続いていく。
作家は、作業過程を通じて経験し、感じたものを観客と共有するために、様々な試みを行ってきた。観客の前で公開制作をし、観客が直接感じるようにしたり、作家の代わりに筆写する装置を考案し、設置された完成作品と共に作業が進行していく過程を見せたりした。今回の展示では、観客が作品を体験できる独立した空間を演出したが、暗い密室のように造り上げた空間の中に入ると、大きなスクリーンが見え、そこに人体のシルエットが巨大に映される。スクリーンに近付いていくと、腕と手の動きに注目できるが、このシルエットは、革に祈りを筆写する作家のものであると推測できる。もし意識できなくても、暗い空間に映された映像の光と静けさの中で、何処からか聞こえてくる風の音、何かを繰り返して書いている巨大な人影の前で、一人で立っている観客は、様々な感覚が敏感に反応し、その時間と空間の中で作品を余不足なく経験できるように導かれる。
今回の展示タイトルである「アナポラ(Anaphora)」は、「思い出すこと(ἀναφορά)」に由来し、修辞技法の中で首句反復を意味する。作家は引き続き祈りを筆写する行為を繰り返し、同時にその行為を通じて人間の本質に対する問題を思い出させたいという意図を含めている。そして上記で言及した映像インスタレーション作品は、「内的平安」という意味の「へシュキア(Hesychia)」という作品名で、俗世に足を掛け生きている人々に精神的な高揚を通じ、内的平安を経験できればという希望的な願いを込めている。
イ・ミンハは、線の濃淡効果を焼きごての温度と筆写する際の手の圧力で調整して出しているが、ひとつひとつ、焼きごてを当て痕跡を残していく作業方式は、水墨画の濃淡表現や一筆書きとの類似点が感じられる。このように伝統絵画の経験を活かしながら、革と焼きごて、映像インスタレーションなど、様々な媒体へと拡張していく彼女の作品の行方は今後どうなるだろう。古代人が燔祭壇を設け、生け贄を焼き、天に捧げる祭祀儀式を通じ、神との疎通を試みたように、作家は革に祈りを焼き刻むことを通じて世と疎通しながら、より高い次元との疎通を熱望しているかもしれない。このような熱望がこれからも表現の方式に拘泥されること無く、発現されてゆくことを期待する。
2014年5月、グロアーツベリーギャラリーでの個展リーフレットから抜粋